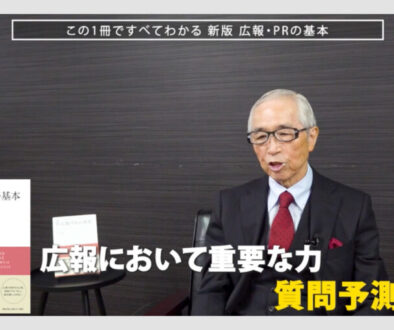日刊工業新聞「主張」:草の根「命名権」で地方創生 中小の活用を促す仕組みを
命名権=Naming(ネーミング) Rights(ライツ)を地方創生の根幹に促進しよう
広報・危機対応コンサルタント 山見博康IMG_20201102「刊工」5面山見博康主張「草の根命名権で地方創生」_0001
この9月誕生した菅義偉新内閣は、コロナ禍の中でも、安倍政権を引き継ぎ経済成長を最重点施策としている。この程発足した「成長戦略会議」でも“足腰強い中小企業育成”が重要課題である。落ち込んだ地方経済浮揚を狙い、「GO TOトラベル」「GO TOイート」等諸施策を講じて地方創生・中小企業活性化を図ろうとしている。
しかし、この方式だけでは観光業や飲食業などへの支援が主体で短期的なので、中小企業全体へは波及せず、長期的な仕組みとしての成長促進にはならない。
地方へ資金還流施策は既に一般化した「ふるさと納税」がある。応援したい自治体に寄付する代わりに返礼品を受けられる制度だが、最近は返礼品目当てが多く本来の使途に使われているかは疑問だ。
そこで、「命名権」に改めて着目し、国の支援により普及させることによって、地方創生や活性化を図る方法を提案したい。
「命名権」とは、企業が、施設建設費や維持費を長期間賄う代わりに、所有者から命名権を得て、長期的にブランド向上や社会貢献・SDGsが図れるWin-Winの仕組みである。
2001年頃、私はある友人から、米国で1990年代から急速に拡大し、「命名権」の導入への協力要請を受けた。イチローのシアトルマリナーズの本拠地「セイフコ・フィールド」も成功例だ。私は仕事柄その優れた有用性を認め、全面支援を約束した。
先ず、サッカーブーム前で閑古鳥が鳴く「東京スタジアム」に着目、東京都やスポンサー数社に提案、それがきっかけで、2003年我が国初の「命名権」である「味の素スタジアム」が実現したのである。
並行して「横浜国際総合競技場」の窮状に鑑み、同じ横浜市民として、トップ当選の最年少市会議員古川なおき先生を訪ねた。先生はこの社会的意義に共感、直ちに市幹部に提案した結果、「日産スタジアム」に加えて「日産本社」招致も実現したのだ。が、その端緒である影の立役者名が公にならず、その惻隠のご功績が本人の内心の誇りに留まっているのが誠に悔しい。
これらの成功が先駆けし少しずつ広がってはいるが、実は私が傾けた本当の想いは「小さな草の根命名権」だ。その利点とは:
1. 小資金でも有志誰でも活用でき、使途が直接で明確である。
2. 中小企業が、社名や商品名・個人名を遺しつつ、故郷・出身地や会社の拠点等々に社会貢献ができる。
3. 地方自治体の膨大な施設すべてを対象にできるので、津々浦々に波及しやすい。老朽化した公民館、公園、歩道橋、駅、バス停・・・工夫次第でアイデアに限りはない!
各自治体の創意工夫によって、多様多彩な命名権が優遇的に利便性良く活用できれば、故郷を離れて事業や何かで得た余裕資金の使途に絶好の大義名分に出来ると期待していた。どんな善行も社会的意義・常識を欠けば、曲解を招く恐れに、常識人程二の足を踏む。そこで大金でなくとも善意の有志が相応の貢献を果せ全国深く普及すると期待していた。
ところが、ここ20年間で今も稼働中は全国で5-600か? スポーツ関係が最も多く、美術館等文化施設、大学など大都市が大半で、全国1771自治体が保有する膨大な公共施設数に比し実に少ないのが実状だ! 例えば、横浜市では、スタジアムの他、公園・トイレ・歩道橋等で11件の命名権が運用されているが全体の施設数に比して余りにも少な過ぎるのではないだろうか?
そこで、私は、新政府や「成長戦略会議」に提案したい。
この「命名権」に対して、税制面の優遇措置や何らかの促進制度など国や自治体の積極的支援協力により、日本経済を支える中小企業が快く活用でき、地方自治体に末永く資金が還流する仕組みを構築することを!