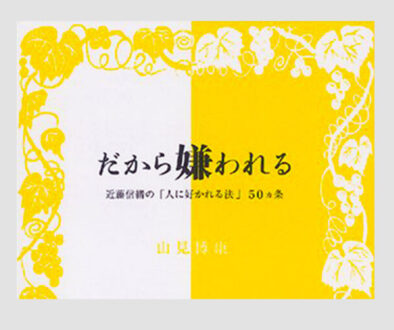だから嫌われる 第7条 見栄がない
第七条 見栄がない
相手の見栄がなんだか判っていれば、いよいよそれを尊重せねばならず、その見栄の正体がわからなければ常にさぐっていなければならない。見当ちがいをすれば機嫌を損ずる。
見栄のない人にはお世辞もいらない。正味の話ができる。約束しても、あとで心配の必要がない。 見栄のない同志では感情の無駄もないし、物の無駄もない。僅かのものを持ち寄っても常に豊かである。見栄のない人は人を豊かにする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
「みえ」には「見栄」と「見得」があります。「見栄」とは「うわべを飾ること。体裁を取り繕うこと」であり、「見得」とは、歌舞伎役者の演技にあるような「ことさら自分を誇示する態度」のことです。
「自分には見栄はない」という人ほど、見栄っ張りの人がいます。要は自分以上のものを見せようとすることです。収入以上のものを買ったり、無いものを有るように見せることもそうでしょう。しかし、それは長続きするはずはありません。化けの皮が剥がれるのは、まさに時間の問題です。
「肉体を包むだけの衣服の色柄などには私は目を向けない。誰も仮面を長いことかぶっていること はできない。偽装はやがて自己の本性に立ち帰る」と古代ローマの哲人セネカも喝破しています。
人は仮面を長くつけておくことはできないのです。宝石や車などの持ち物を自慢する人がいますが、これらは本当の自分のものではなく、今、単に自分に付着しているものでありましょう。刹那的(せつなてき)なものなのです。それを自慢する人は、付着物を誇ることになります。
つまり、衣服のシミを誇ることと同じです。自尊心が少しあればきっと恥ずかしく思うことでしょう。そう思って、持ち主の顔や姿をよく見なおすと前とは違って見えてくるにちがいありません。 本当の自分のものは、自分の力で成し得たことや自分の創意で造ったもの、あるいは自分の内面から発露する思想や考え方などです。小さくてもいい、それを誇れるようになると本当に“見得”を切ることもできましょう。
しかし、おろかな行為と判ってはいても、時に誘惑に負けて見栄を張り、あとで恥ずかしい思いをすることも、人間ですから、ままあります。ところが、そんな見栄は期待した効果は得られないどころか、逆に悪化するものです。
とはいっても、見栄を張ろうとすることを否定することはありません。なぜなら、「見栄」はいわば「意地」や「負けじ魂」の別な形ともいえるからです。時に応じて「ここはその位の見栄を張ってやろうではないか!」という態度は、ある意味では必要な自負心に近いものではないでしょうか? それは、時には「見得」と呼べるものでしょう。
子供の頃から考えると、誰でも何度か「見得を切ったこと」を思い出します。 ちょっと上手にお絵かきして、お母さんに誉められた時、運動会で一番になった時、凧(たこ)揚げでもっとも高くあげたとき、学芸会でいい役をした時・・・それに大人になっても写真を写るときには、だれもがポーズを作り、見得を切っています。誰しも自分が日々演じる役どころで、適切な見得を切りたいものです。
「見栄」も「見得」も使いどころさえ間違わなければ、自分を鼓舞したり、勇気付けたり、高めたりする一つの方法になることを覚えていたいものです。カッコよく見栄を張り、程よく見得を切れる人は、周りの人にも何かさわやか感を残し、少しでも力を与えていく人のようです。 真に見栄のない人は、貴重な人です。
いつでも、どこでも、見栄っ張り・・・だから嫌われる